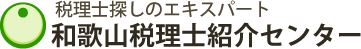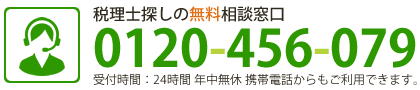宮澤税理士事務所
| 1 | 和歌山県 | 宮澤税理士事務所 |
|---|
| 皆様と共に発展を! 税務会計から経営・管理の問題等何でも相談できる身近な税理士事務所です。もちろん、税務調査や事業者以外の方の相続・贈与等も確実対応! 26年の税務署勤務を経て開業しました。調査や徴収事務等で様々な業種の方に接してきた経験を活かして、皆様の信頼にお応えします! |
| 職員人数 | 税理士1人 その他1人 |
|---|---|
| 所長の年齢 | 62歳 |
| 職員平均年齢 | 46歳 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 土日祝休 (時間外・休日対応可) |
| 設立 | 平成21年9月 |
| 所属団体など | 近畿税理士会 海南支部 |
| 顧問先 | 小売卸売業・製造業・サービス業・不動産業・医業他各種 |
| 料金 | 法人月次(顧問・決算・申告書作成料の年間総額)96,600円〜、個人月次(前掲同様)60,900円〜、個人年次(決算書・申告書作成)31,500円〜、相続税申告150,000円〜、その他。(詳細は面談の上) |
| 対応地域について | 和歌山、大阪 |
| 取扱業務 | |
| 得意業種 | |
| 対応ソフト |
| 社名 | 宮澤税理士事務所 |
|---|---|
| 住所 | 和歌山県海南市日方1182番地4 |
| アクセス方法 | JR紀勢線「海南駅」から徒歩15分程度、事務所前に「藤白」バス停有。 阪和高速「海南IC」を出てスグ(駐車場有)。 |
宮澤税理士事務所の税金相談履歴
確定申告について
私は、主人の扶養家族になっています。パートを2つ掛け持ちしだしました。今年は、103万以内におさめ、来年は、130万以内におさめようと思っていますが、どちらの年も確定申告しなければならないのですか。
Re:確定申告について
はじめまして
パート2つの掛け持ちとのことですので、年末調整等がなされていないこと、他に所得がないことを前提で、国税(所得税)に関しての回答をさせていただきます。
103万円までの年間収入(パート給与)なら税務署への確定申告の必要はありません。
1,030,000−650,000(給与所得控除)=380,000(給与所得)
他に所得があれば話は変わりますが、所得が38万円までなら配偶者等の控除対象にもなれます。
ご自身に関しては、基礎控除(38万円)を差し引くと課税される所得は0になるので、控除された源泉所得税があれば申告して還付を受けれます。
その際の申告は義務ではありません。
パート収入が103万円を超えた場合は、基礎控除の他の控除(生命保険料控除等)の有無にもよりますが、課税される所得が発生する可能性があります。
この場合、以下の計算で算定した税額と、源泉徴収されている税額を比較して、源泉徴収額が少なければ申告して差額を納税する必要があります。源泉徴収額が多ければ申告すれば還付を受けれます。
給与収入 − 650,000円 − 380,000(基礎控除) − その他の控除額 = A
Aについて1,000円未満の端数は切り捨て = A’
A’×5%
※給与収入を162万円までに限定した回答です。
ただし、パート収入が103万円を超える場合は、配偶者控除や扶養控除の対象にはなれません。
(配偶者関係の場合は、妻のパート収入が103万円から141万円までの間なら、夫には妻の所得に応じた配偶者特別控除の適用があります。)
宮澤税理士事務所
パート2つの掛け持ちとのことですので、年末調整等がなされていないこと、他に所得がないことを前提で、国税(所得税)に関しての回答をさせていただきます。
103万円までの年間収入(パート給与)なら税務署への確定申告の必要はありません。
1,030,000−650,000(給与所得控除)=380,000(給与所得)
他に所得があれば話は変わりますが、所得が38万円までなら配偶者等の控除対象にもなれます。
ご自身に関しては、基礎控除(38万円)を差し引くと課税される所得は0になるので、控除された源泉所得税があれば申告して還付を受けれます。
その際の申告は義務ではありません。
パート収入が103万円を超えた場合は、基礎控除の他の控除(生命保険料控除等)の有無にもよりますが、課税される所得が発生する可能性があります。
この場合、以下の計算で算定した税額と、源泉徴収されている税額を比較して、源泉徴収額が少なければ申告して差額を納税する必要があります。源泉徴収額が多ければ申告すれば還付を受けれます。
給与収入 − 650,000円 − 380,000(基礎控除) − その他の控除額 = A
Aについて1,000円未満の端数は切り捨て = A’
A’×5%
※給与収入を162万円までに限定した回答です。
ただし、パート収入が103万円を超える場合は、配偶者控除や扶養控除の対象にはなれません。
(配偶者関係の場合は、妻のパート収入が103万円から141万円までの間なら、夫には妻の所得に応じた配偶者特別控除の適用があります。)
宮澤税理士事務所
会社設立について
はじめまして。
現在、カナダで暮らしている日本人です。
配偶者の仕事の都合による一時的(数年)な海外居住です。
このたび、日本国内向けのオンラインショッピングサイトを立ち上げる事になり、同時に会社を設立する事になりました。
日本に居住するスタッフが日本で仕入れた商品を日本で販売するのですが、サイトの所有者である私自身は海外でサイトの運用業務を行います。
この場合、
(1)サイト保有者である私が居住しているカナダで法人設立するべきか、サービスを提供する日本で法人設立するべきか
(2)私自身の納税義務はどの国で発生するか
(3)日本の税務署に対して事業者登録などを行う必要があるか
上記3点につきまして、アドバイスをいただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
現在、カナダで暮らしている日本人です。
配偶者の仕事の都合による一時的(数年)な海外居住です。
このたび、日本国内向けのオンラインショッピングサイトを立ち上げる事になり、同時に会社を設立する事になりました。
日本に居住するスタッフが日本で仕入れた商品を日本で販売するのですが、サイトの所有者である私自身は海外でサイトの運用業務を行います。
この場合、
(1)サイト保有者である私が居住しているカナダで法人設立するべきか、サービスを提供する日本で法人設立するべきか
(2)私自身の納税義務はどの国で発生するか
(3)日本の税務署に対して事業者登録などを行う必要があるか
上記3点につきまして、アドバイスをいただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
Re:会社設立について
はじめまして
居住者・非居住者の取扱いについては、微妙な違いで異なることとなりますので、ご質問状況から当方判断で回答させていただく点、ご留意ください。
1 カナダと日本の法人税等の実効税率の違いを除けば、数年の居住とのことですし、全ての拠点が日本にあって、スタッフも…とのことですから、日本で設立しておく方が便利ではないかと思います。
2 日本では非居住者となるでしょうから、日本の法人から得る給与等の収入についても、カナダで得る収入があればそれと合わせて、納税義務はカナダに帰属します。
ただし、日本の法人からの給与については、日本国内で20%の源泉所得税が差し引かれることとなり、これはカナダでの申告に際して、外国税額控除としてカナダでの納税額から差し引かれることになります。
3 日本で法人を設立することになれば、日本の法務局で設立登記をすることはもちろんですが、税務署に対しても法人の設立届けや給与支払事務所の開設届け他、青色関係、源泉所得税関係・減価償却関係等の該当する届出書を提出の上、以降、確定申告等を行う必要があります。
居住者・非居住者の取扱いについては、微妙な違いで異なることとなりますので、ご質問状況から当方判断で回答させていただく点、ご留意ください。
1 カナダと日本の法人税等の実効税率の違いを除けば、数年の居住とのことですし、全ての拠点が日本にあって、スタッフも…とのことですから、日本で設立しておく方が便利ではないかと思います。
2 日本では非居住者となるでしょうから、日本の法人から得る給与等の収入についても、カナダで得る収入があればそれと合わせて、納税義務はカナダに帰属します。
ただし、日本の法人からの給与については、日本国内で20%の源泉所得税が差し引かれることとなり、これはカナダでの申告に際して、外国税額控除としてカナダでの納税額から差し引かれることになります。
3 日本で法人を設立することになれば、日本の法務局で設立登記をすることはもちろんですが、税務署に対しても法人の設立届けや給与支払事務所の開設届け他、青色関係、源泉所得税関係・減価償却関係等の該当する届出書を提出の上、以降、確定申告等を行う必要があります。
扶養家族になった場合のデメリットについて
・73歳になる母は、国民年金と遺族年金を受給しています。保険は国民保険で1割負担となっています。
・現在別居中の兄が、母を別居の扶養家族として申請しようかと検討しています。
【質問1】この場合、兄がなんらかの費用を母に払うということになると思うのですが、母が扶養家族となった場合、母側にデメリットはないでしょうか?
【質問2】追加の収入があるとみなされ、税金があがったりすることはないでしょうか?
【質問3】扶養家族になり、国民年金から厚生年金に変更することになるのでしょうか?その場合、保険の負担割合があがるということはないでしょうか?
・現在別居中の兄が、母を別居の扶養家族として申請しようかと検討しています。
【質問1】この場合、兄がなんらかの費用を母に払うということになると思うのですが、母が扶養家族となった場合、母側にデメリットはないでしょうか?
【質問2】追加の収入があるとみなされ、税金があがったりすることはないでしょうか?
【質問3】扶養家族になり、国民年金から厚生年金に変更することになるのでしょうか?その場合、保険の負担割合があがるということはないでしょうか?
Re:扶養家族になった場合のデメリットについて
はじめまして
扶養親族といっても、税法上・健康保険上・勤務先手当て他、取扱いは様々です。
ここでは、特に税法上を考慮して回答させていただきます。
また、お母さんの年金収入は扶養家族になれる範囲で、現在誰の扶養にもなっていないとの前提です。
1 扶養しているという限りは、被扶養者の生計費の負担(全部又は一部)等があってしかるべきですね。
税法上の扶養家族であれば、生活費等の仕送りをして、その旨記録等を残しておく必要があります(実際に税務署から確認されることはほとんどありませんが…)。
その上で、確定申告で扶養家族として申告書に記載して控除を適用すればOKです。
お兄さんが給与所得者なら、年末調整済の給与(源泉徴収表)に扶養控除のみを追加する申告になりますし、勤務先に扶養家族(税法上のみ)と届出して、年末調整で精算しておくことも可能です。
※勤務先手当て等の問題は、別途、勤務先にお尋ねください。
その他、福祉上の問題として、将来的にお母さんが施設に入ったりという際、公共施設等であれば、世帯所得に応じて料金を算定することになるかと思われますが、別居ということで住民票が別世帯であれば、あくまでお母さんの所得によってのみ算定されることになると思います。
以上のことから、あくまで私見ではありますが、大きなデメリット等はないものと考えます。
2 所得税についていえば、あくまで各個人に対して算定するものですから、扶養に入っても収入が変わることはありませんし(仕送りの金銭はあくまで生活費で税法上等の収入ではありません)、なんら変わることはありません。
3 年金はすでに受給されている方なので関係ありません。健康保険のことかと思われますので、このことについて回答させていただきます。
税法上のみの扶養家族なら、健康保険はあくまでお母さん個人として現状のままとすることができます(可能であればお兄さんの健康保険に入れた方が掛け金の負担等は有利だと思いますが)。
お兄さんの社会保険に入れるのであれば、勤務先等への届出が必要ですので、給与上の扶養家族(手当等)と合わせて勤務先にたずねていただくのが一番です。
扶養親族といっても、税法上・健康保険上・勤務先手当て他、取扱いは様々です。
ここでは、特に税法上を考慮して回答させていただきます。
また、お母さんの年金収入は扶養家族になれる範囲で、現在誰の扶養にもなっていないとの前提です。
1 扶養しているという限りは、被扶養者の生計費の負担(全部又は一部)等があってしかるべきですね。
税法上の扶養家族であれば、生活費等の仕送りをして、その旨記録等を残しておく必要があります(実際に税務署から確認されることはほとんどありませんが…)。
その上で、確定申告で扶養家族として申告書に記載して控除を適用すればOKです。
お兄さんが給与所得者なら、年末調整済の給与(源泉徴収表)に扶養控除のみを追加する申告になりますし、勤務先に扶養家族(税法上のみ)と届出して、年末調整で精算しておくことも可能です。
※勤務先手当て等の問題は、別途、勤務先にお尋ねください。
その他、福祉上の問題として、将来的にお母さんが施設に入ったりという際、公共施設等であれば、世帯所得に応じて料金を算定することになるかと思われますが、別居ということで住民票が別世帯であれば、あくまでお母さんの所得によってのみ算定されることになると思います。
以上のことから、あくまで私見ではありますが、大きなデメリット等はないものと考えます。
2 所得税についていえば、あくまで各個人に対して算定するものですから、扶養に入っても収入が変わることはありませんし(仕送りの金銭はあくまで生活費で税法上等の収入ではありません)、なんら変わることはありません。
3 年金はすでに受給されている方なので関係ありません。健康保険のことかと思われますので、このことについて回答させていただきます。
税法上のみの扶養家族なら、健康保険はあくまでお母さん個人として現状のままとすることができます(可能であればお兄さんの健康保険に入れた方が掛け金の負担等は有利だと思いますが)。
お兄さんの社会保険に入れるのであれば、勤務先等への届出が必要ですので、給与上の扶養家族(手当等)と合わせて勤務先にたずねていただくのが一番です。
正社員から専業主婦になった場合の医療保険、個人年金について。
質問させていただきます。
妻ですが、今までずっと正社員で共働きだったため妻の会社の年末調整で妻名義の医療保険(月3800円)、個人年金(月7000円)、住宅ローンの控除(55000円ですが、年末調整で控除しきれないため住民税が割引になってました)。現在育児休暇中で育児手当が出ております。会社都合による退社をすることがきまり、このまま仕事復帰しないまま育児休暇終了後から2か月有休消化し、その後9月から失業手当をいただきながら求職し、決まらなければ12月から私の扶養とししばらく専業主婦の予定です。
失業保険、育児手当は非課税で、課税対象となる2か月の給与も合わせても20万ほどです。
その上での質問です。年末には扶養になる妻の医療保険、個人年金は私の年末調整で記入してもよいのでしょうか?契約者も被契約者も口座も妻の状態ですが、収入がほとんどないためいつも私の給料と妻の手当を合わせた中から妻口座にいれてきました、さらに完全に収入がなくなるのでこれからも私が扶養している妻の口座にお金をいれることになりそうです。
また、もしわたしの年末調整で今年控除をおこなったとして、数年後から妻がまたどこかで働き年末調整がきたら、また妻のほうで控除させていいのでしょうか?
しなければならないこと、注意点などもありましたらご指導ねがいます。乱文、長文申し訳ございません。
妻ですが、今までずっと正社員で共働きだったため妻の会社の年末調整で妻名義の医療保険(月3800円)、個人年金(月7000円)、住宅ローンの控除(55000円ですが、年末調整で控除しきれないため住民税が割引になってました)。現在育児休暇中で育児手当が出ております。会社都合による退社をすることがきまり、このまま仕事復帰しないまま育児休暇終了後から2か月有休消化し、その後9月から失業手当をいただきながら求職し、決まらなければ12月から私の扶養とししばらく専業主婦の予定です。
失業保険、育児手当は非課税で、課税対象となる2か月の給与も合わせても20万ほどです。
その上での質問です。年末には扶養になる妻の医療保険、個人年金は私の年末調整で記入してもよいのでしょうか?契約者も被契約者も口座も妻の状態ですが、収入がほとんどないためいつも私の給料と妻の手当を合わせた中から妻口座にいれてきました、さらに完全に収入がなくなるのでこれからも私が扶養している妻の口座にお金をいれることになりそうです。
また、もしわたしの年末調整で今年控除をおこなったとして、数年後から妻がまたどこかで働き年末調整がきたら、また妻のほうで控除させていいのでしょうか?
しなければならないこと、注意点などもありましたらご指導ねがいます。乱文、長文申し訳ございません。
Re:正社員から専業主婦になった場合の医療保険、個人年金について。
はじめまして
1 奥様の収入が、ご記載の年間収入であれば、当年
は貴方の控除対象配偶者とすることが可能です。
〔年間所得38万円まで(給与等なら収入103万円まで/93万円を超えると奥様に別途住民税が課税されます。)〕
2 控除対象か否かにかかわらず、生計を一にする親
族の社会保険料・生命保険料等を、貴方が負担した
場合は、貴方の控除対象とすることができます。
※「貴方が負担した」とは実質的に負担したこと
を云いますので、奥様の給与等から控除された
ものは含みません。
また、口座振替に関しては後期高齢者保険料
等において、口座名義人が負担者であるとの形
式認定の取り扱いがありますが、ここでは説明
を省略させていただきます。
3 奥様分の社会保険料や生命保険料を貴方で控除適
用した場合でも、翌年以降、奥様に収入ができれば
必要に応じて奥様で適用できます。
4 社会保険料控除や生命保険料控除は、生計一の親
族分を負担した際に、負担した人が控除できる制度
ですが、客観的に負担者が判明する他は、その負担
者の表明は自主申告によっています。
つまり、貴方が負担したものなら、妻宛の控除証
明書や領収書を添付してもOKということです。
※負担者に関しては、以上勘案の上ご判断ください。
1 奥様の収入が、ご記載の年間収入であれば、当年
は貴方の控除対象配偶者とすることが可能です。
〔年間所得38万円まで(給与等なら収入103万円まで/93万円を超えると奥様に別途住民税が課税されます。)〕
2 控除対象か否かにかかわらず、生計を一にする親
族の社会保険料・生命保険料等を、貴方が負担した
場合は、貴方の控除対象とすることができます。
※「貴方が負担した」とは実質的に負担したこと
を云いますので、奥様の給与等から控除された
ものは含みません。
また、口座振替に関しては後期高齢者保険料
等において、口座名義人が負担者であるとの形
式認定の取り扱いがありますが、ここでは説明
を省略させていただきます。
3 奥様分の社会保険料や生命保険料を貴方で控除適
用した場合でも、翌年以降、奥様に収入ができれば
必要に応じて奥様で適用できます。
4 社会保険料控除や生命保険料控除は、生計一の親
族分を負担した際に、負担した人が控除できる制度
ですが、客観的に負担者が判明する他は、その負担
者の表明は自主申告によっています。
つまり、貴方が負担したものなら、妻宛の控除証
明書や領収書を添付してもOKということです。
※負担者に関しては、以上勘案の上ご判断ください。
損益通算、財産分与
損益通算、財産分与についての相談ですが。現在、給与所得が3千万程度あり節税対策を考えています。また、私の両親が持ち家(数件あり)の賃貸を行っていますが、いずれはこの物件を贈与されることとなるのですが。生前に私が贈与税がかかる分を損益が出るようにローンを組んで持ち家を生前購入(2〜3千万程度)し、損益通算を利用して給与所得の減税を計ることは可能でしょうか。ご教授よろしくお願いします。
増井
増井
Re:損益通算、財産分与
はじめまして
以下の問題点があります。
1 売買は時価で行う必要があります。
2 親子間の売買では、ローンを組めないケースがほと
んどです。
3 不動産所得で赤字が出れば損益通算できますが、仮
にローンを組んでも、赤字の内、土地部分の利息分は
損益通算できません。
ご両親の不動産所得が経常的に赤字で、ご両親に損
益通算できる所得がないとか、あっても税額的に貴方
で適用した方が相当有利といった場合に名義変更する
ことのメリットが期待できると考えられますが、売買
取得においては上記のとおり、時価相当の金銭の準備
が必要になります。
不動産価格や不動産所得(赤字)の規模がわからない
ので回答しづらいですが、売買の場合の資金準備・贈
与の場合の税額・損益通算により期待できる節税額(
中長期年間)・連年の赤字負担…等、総合的に勘案し
て判断する必要があると思われます。
※不動産赤字額 > 節税額(給与源泉の還付税額)
以下の問題点があります。
1 売買は時価で行う必要があります。
2 親子間の売買では、ローンを組めないケースがほと
んどです。
3 不動産所得で赤字が出れば損益通算できますが、仮
にローンを組んでも、赤字の内、土地部分の利息分は
損益通算できません。
ご両親の不動産所得が経常的に赤字で、ご両親に損
益通算できる所得がないとか、あっても税額的に貴方
で適用した方が相当有利といった場合に名義変更する
ことのメリットが期待できると考えられますが、売買
取得においては上記のとおり、時価相当の金銭の準備
が必要になります。
不動産価格や不動産所得(赤字)の規模がわからない
ので回答しづらいですが、売買の場合の資金準備・贈
与の場合の税額・損益通算により期待できる節税額(
中長期年間)・連年の赤字負担…等、総合的に勘案し
て判断する必要があると思われます。
※不動産赤字額 > 節税額(給与源泉の還付税額)
その他の税理士
よく検索されるキーワード
- 貸借対照表|
- 品川区 税理士|
- 給与 税金|
- 年調・社保算定|
- 会計事務所|
- 予定納税|
- 生前贈与|
- 資産運用|
- 堀口会計|
- 所得税|
- 税理士 千葉県|
- 税理士紹介|
- 決算書作成|
- 建設業手続代行|
- 株式公開支援|
- 税理士事務所|
- 飲食店 税理士|
- 助成金|
- 直系卑属|
- 農業|
- 印紙税|
- 使途不明金|
- 源泉徴収|
- 福井県 節税|
- 税理士 西宮|
- 決算|
- 税理士協会|
- 定款|
- 確定申告|
- 扶養控除|
- 相続税|
和歌山税理士紹介センターの税理士検索をお使いのうえで、ご不明な点がございましたら、よくあるご質問をご覧ください。
よくあるご質問で解決できない問題や、その他ご意見などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。