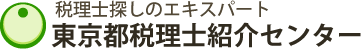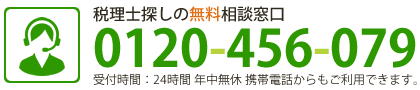はざま会計事務所
| 1 | 東京都 | はざま会計事務所 |
|---|

|
当事務所は、小平市、小金井市、西東京市、武蔵野市、東久留米市、清瀬市、東村山市を中心とした地域に密着した活動を行っております。 お客様に喜んで頂く事を第一に考えておりますので、どんな些細な点もお気軽にご相談ください。 初回相談料は、無料です。 |
| 職員人数 | 巡回監査1人 事務員1人 |
|---|---|
| 所長の年齢 | 67歳 |
| 職員平均年齢 | 45歳 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 土日祝日休み |
| 設立 | 平成28年 4月 |
| 所属団体など | 東京税理士会 |
| 顧問先 | 月次顧問先25件 |
| 料金 | 当事務所規程による |
| 対応地域について | 東京、千葉、埼玉、神奈川 |
| 取扱業務 | |
| 得意業種 | |
| 対応ソフト |
| 社名 | はざま会計事務所 |
|---|---|
| 住所 | 東京都東久留米市花小金井1-6-32 共立ビル3F |
| アクセス方法 | 西武新宿線「花小金井」駅 北口より徒歩4分 |
はざま会計事務所の税金相談履歴
相続について
質問させていただきます。
土地は長男、家屋は次男の所有です
長男夫婦には子供がなく、別の場所に
住んでいます。(長男所有)
次男は独身で、質問の土地に住んでいます
三男は 質問の土地の一部にて商売を
しています。三男死後、三男の長男が引き継いでいます。
家賃は発生してません
長男の兄弟は、長男夫婦 次男 長女
夫婦(子供1) 三男夫婦(三男 死亡)(子供2)
長男妻の兄弟は2人居ます。
? 長男が亡くなった場合
通常は、妻が100%相続でよいのでしょうか?
? 妻が相続を一部(質問の土地)
放棄した場合、誰が相続の対象になるのでしょうか?
土地は長男、家屋は次男の所有です
長男夫婦には子供がなく、別の場所に
住んでいます。(長男所有)
次男は独身で、質問の土地に住んでいます
三男は 質問の土地の一部にて商売を
しています。三男死後、三男の長男が引き継いでいます。
家賃は発生してません
長男の兄弟は、長男夫婦 次男 長女
夫婦(子供1) 三男夫婦(三男 死亡)(子供2)
長男妻の兄弟は2人居ます。
? 長男が亡くなった場合
通常は、妻が100%相続でよいのでしょうか?
? 妻が相続を一部(質問の土地)
放棄した場合、誰が相続の対象になるのでしょうか?
Re:相続について
税理士の間と申します。
ご長男に親御さんがいらっしゃれば、配偶者と親御さんで、もしいらっしゃらなければ、配偶者とご長男のご兄弟です。
一部放棄というのは、”土地はいらないけど、適法に相続権を放棄ということはしない”ということですか?
ならば、その土地は、他の相続人が話し合って決めるだけです。
ご長男に親御さんがいらっしゃれば、配偶者と親御さんで、もしいらっしゃらなければ、配偶者とご長男のご兄弟です。
一部放棄というのは、”土地はいらないけど、適法に相続権を放棄ということはしない”ということですか?
ならば、その土地は、他の相続人が話し合って決めるだけです。
相続税の件
質問させて下さい。
今年9月父・10月に母が亡くなりました。住宅、預金等を兄弟二人で相続したいのですが、
父名義の遺産の基礎控除7000万円・母名義の遺産基礎控除7000万で兄弟二人で14000万円まで無税でいけますか?
それとも一家で基礎控除7000万かな?
お願いします。
今年9月父・10月に母が亡くなりました。住宅、預金等を兄弟二人で相続したいのですが、
父名義の遺産の基礎控除7000万円・母名義の遺産基礎控除7000万で兄弟二人で14000万円まで無税でいけますか?
それとも一家で基礎控除7000万かな?
お願いします。
Re:相続税の件
税理士の間と申します。
先にお父様がなくなった時点で、基礎控除額は3人で
8,000万円、お母様がなくなった時点で、基礎控除額は2人で7,000万円をそれぞれの遺産額から控除します。
先にお父様がなくなった時点で、基礎控除額は3人で
8,000万円、お母様がなくなった時点で、基礎控除額は2人で7,000万円をそれぞれの遺産額から控除します。
源泉徴収義務
業界団体の支部役員です。
このたび、外部講師に講演を委託することになりました。
この場合の講演料は、源泉徴収する義務があるのでしょうか。
ちなみにこういう場合は本部では源泉徴収しております。
支部といっても、本部から活動費をいただいて運営しているだけで、
法人等の登記をしておりません。
また、時々役所から、相談会に会員を派遣してくれと依頼を受けることがあり、
その際はいったん支部に入金したうえで、謝金として派遣した会員に支給しています。
この場合についても、報酬として源泉徴収する義務の有無について教えてください。
このたび、外部講師に講演を委託することになりました。
この場合の講演料は、源泉徴収する義務があるのでしょうか。
ちなみにこういう場合は本部では源泉徴収しております。
支部といっても、本部から活動費をいただいて運営しているだけで、
法人等の登記をしておりません。
また、時々役所から、相談会に会員を派遣してくれと依頼を受けることがあり、
その際はいったん支部に入金したうえで、謝金として派遣した会員に支給しています。
この場合についても、報酬として源泉徴収する義務の有無について教えてください。
Re:源泉徴収義務
税理士の間と申します。
まず、本部で源泉徴収をしていれば、10%控除後の金額を支払えばいいと思います。
また、役所から総額を入金していれば、支部で源泉徴収をすればいいと思います。
まず、本部で源泉徴収をしていれば、10%控除後の金額を支払えばいいと思います。
また、役所から総額を入金していれば、支部で源泉徴収をすればいいと思います。
高度障害の贈与税
ご質問内容
質問させていただきます。
現在入院中の実母に保険会社から
「高度障害保険金」がおりました。
受取人と代理請求人は、一人っ子である私です。
(実父とは離婚しております)
私は母とは暮らしておりませんで
現在、介護施設でお世話になっております。
今後、介護施設へのお金などは今回の保険金で、私の方で行っていく予定です。
「保険内容」
契約者、被保険者→実母
受取人(代理請求人)→実子である私
保険料支払い→実母(実母が数十年、ここ5年間は実の子供の私が振り込んでいました)
受取金額 2,000万円
≪質問1≫
高度障害保険金が、私の指定口座に入金されました。
どのような税金がかかりますか?
母の為に使う(実母の銀行口座へ振り込)事は税金は発生しないと思います。それ以外、そのお金を引き出して母に会いに行く高速代などや自動車の費用など(直接、実母に掛ったと証明出来ないもの)で使用した場合、贈与税は発生致しますか?
≪質問2≫
質問1で税金が掛らない場合でも、亡くなったあとで、質問1などで使用した金額や残りの金額に相続税は掛りますか?
お手数ですが、ご教示宜しくお願い致します。
質問させていただきます。
現在入院中の実母に保険会社から
「高度障害保険金」がおりました。
受取人と代理請求人は、一人っ子である私です。
(実父とは離婚しております)
私は母とは暮らしておりませんで
現在、介護施設でお世話になっております。
今後、介護施設へのお金などは今回の保険金で、私の方で行っていく予定です。
「保険内容」
契約者、被保険者→実母
受取人(代理請求人)→実子である私
保険料支払い→実母(実母が数十年、ここ5年間は実の子供の私が振り込んでいました)
受取金額 2,000万円
≪質問1≫
高度障害保険金が、私の指定口座に入金されました。
どのような税金がかかりますか?
母の為に使う(実母の銀行口座へ振り込)事は税金は発生しないと思います。それ以外、そのお金を引き出して母に会いに行く高速代などや自動車の費用など(直接、実母に掛ったと証明出来ないもの)で使用した場合、贈与税は発生致しますか?
≪質問2≫
質問1で税金が掛らない場合でも、亡くなったあとで、質問1などで使用した金額や残りの金額に相続税は掛りますか?
お手数ですが、ご教示宜しくお願い致します。
Re:高度障害の贈与税
税理士の間と申します。
質問1について
契約者(保険料負担者)→お母さん
被保険者→お母さん
受取人(代理請求人)→あなた
契約内容から、高度障害保険金が振り込まれた時点で、
残念ながら、あなたに231万円の贈与税がかかってしまいます。
質問2について
質問1で贈与税が発生したことによってあなたのものになるので、その後の税金は発生しません。
質問1について
契約者(保険料負担者)→お母さん
被保険者→お母さん
受取人(代理請求人)→あなた
契約内容から、高度障害保険金が振り込まれた時点で、
残念ながら、あなたに231万円の贈与税がかかってしまいます。
質問2について
質問1で贈与税が発生したことによってあなたのものになるので、その後の税金は発生しません。
相続税の基礎控除額について
法定相続人不在で、遺言公正証書による100%遺贈になります。一方、基礎控除として、「基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」がありますが、100%遺贈の場合の基礎控除額は、0円 若しくは、5,000万円のどちらになるか教えて下さい。
Re:相続税の基礎控除額について
税理士の間です。
遺言による遺贈であろうと、分割であろうと、遺産に係る基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)です。
遺言による遺贈であろうと、分割であろうと、遺産に係る基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)です。
同じ地域で検索する
その他の税理士
よく検索されるキーワード
- 記帳代行|
- 資産運用|
- 相続放棄申述受理証明書|
- 滋賀 税理士|
- 給与計算|
- 特別縁故者|
- 社会保険料|
- 労災|
- 予定納税|
- 建設業手続代行|
- 雑損控除|
- 必要経費|
- 定款|
- 直系卑属|
- 助成金|
- 土地建物名義変更|
- 会計事務所|
- 顧問料|
- 税理士 武蔵野市|
- 公証人|
- 法人税|
- 建設業|
- 税理士会|
- 特別償却|
- 帳簿|
- 印紙税|
- 株式公開支援|
- 貸借対照表|
- サービス業|
- 農業|
- 白色申告|
- 土地の贈与|
- 税金対策|
- 税理士事務所|
- 生前贈与|
- 千代田区 会計事務所|
- 確定申告|
- 給与 税金|
- 決算書作成|
- 相続税 相談|
東京都税理士紹介センターの税理士検索をお使いのうえで、ご不明な点がございましたら、よくあるご質問をご覧ください。
よくあるご質問で解決できない問題や、その他ご意見などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。