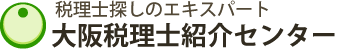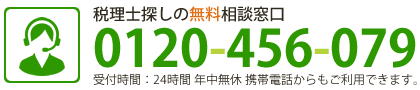たつだ会計事務所
| 1 | 大阪府 | たつだ会計事務所 |
|---|

|
お客様目線を忘れず対応することを心がけています。 会社設立相談、業務効率化、資金繰りなどお気軽にご相談ください。 信頼できる会計・税務のパートナーとして企業の成長をサポートいたします。 |
| 職員人数 | 税理士1人 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00〜17:00 土日祝休み |
| 設立 | 平成24年7月 |
| 所属団体など | 近畿税理士会 |
| 料金 | 顧問料 月額10,500円から 売上規模、訪問回数、作業量によって異なります。 |
| 対応地域について | 大阪府全域の他、和歌山、奈良、兵庫、京都も場所によっては対応可 |
| 取扱業務 | |
| 得意業種 | |
| 対応ソフト |
| 社名 | たつだ会計事務所 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府岸和田市荒木町1-4-53 |
たつだ会計事務所の税金相談履歴
所得税の金額、法人化すべきかどうか
質問させていただきます。
特に所得税の金額と節税について教えていただきたいです。
私はIT系の中小企業の役員です。30代男性、既婚です。
役員報酬は、年間280万円程度です。
これとは別に、今年から個人でビジネスを始め、
こちは、年間1千万円程度の収入になりそうです。
ビジネスの内容はWEBサイトの運営です。
収入源はそのWEBサイトの広告費です。
直接の経費はパソコンやサーバ台など50万円程度です。
その他の経費として、自宅で作業しているため、
家賃(住宅ローン)の半分を経費に計上したいと考えています。
教えていただきたい点は以下の5点です。
・所得税の金額とその他の税金の金額
・節税の方法
・法人化すべきか
・IT系の中小企業の役員が、別の会社を建てて問題ないか
・相談すべき相手
以上、よろしくお願い申し上げます。
特に所得税の金額と節税について教えていただきたいです。
私はIT系の中小企業の役員です。30代男性、既婚です。
役員報酬は、年間280万円程度です。
これとは別に、今年から個人でビジネスを始め、
こちは、年間1千万円程度の収入になりそうです。
ビジネスの内容はWEBサイトの運営です。
収入源はそのWEBサイトの広告費です。
直接の経費はパソコンやサーバ台など50万円程度です。
その他の経費として、自宅で作業しているため、
家賃(住宅ローン)の半分を経費に計上したいと考えています。
教えていただきたい点は以下の5点です。
・所得税の金額とその他の税金の金額
・節税の方法
・法人化すべきか
・IT系の中小企業の役員が、別の会社を建てて問題ないか
・相談すべき相手
以上、よろしくお願い申し上げます。
Re:所得税の金額、法人化すべきかどうか
大阪府岸和田市のたつだ会計事務所です。
質問について、お答えします。
・所得税の金額とその他の税金の金額
税金の計算について、給与収入280万円、事業所得(事業のもうけ)900万円、所得控除100万円として計算すると、所得税169万円、住民税97万円となります。
(所得控除とは、社会保険料、扶養控除、基礎控除などのことです。)
その他、事業税が30万円ぐらいかかる可能性があります。
但し、個人事業税については、事業税の事業区分に該当しない場合は課税されません。
住宅ローンを経費にするとのことですが、経費になるのは利息部分だけです。
また、事業分と家事分との按分はおおまかでも根拠が必要ですので、ご注意ください。
・節税の方法
・法人化すべきか
法人化することにより、節税が可能です。
但し、法人化するには費用が20-30万円必要になります。
・IT系の中小企業の役員が、別の会社を建てて問題ないか
役員になっておられる企業の事業内容によっては問題が生じるかもしれません。
取締役には会社に対する忠実義務があり、そのなかに競業避止義務というものがあります。
取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、会社の承認を受けなければならなりません(会社法356条)。
ただ、競業避止義務は会社組織であればダメで、個人事業であればいいというものではありません。
そのため、別の会社を設立するか否かの前に、競業避止義務の問題があるかもしれません。
・相談すべき相手
税金については税理士、会社設立については司法書士です。
当事務所でも相談を受け付けておりますので、お気軽ご相談ください。
以上、参考になれば幸いです。
質問について、お答えします。
・所得税の金額とその他の税金の金額
税金の計算について、給与収入280万円、事業所得(事業のもうけ)900万円、所得控除100万円として計算すると、所得税169万円、住民税97万円となります。
(所得控除とは、社会保険料、扶養控除、基礎控除などのことです。)
その他、事業税が30万円ぐらいかかる可能性があります。
但し、個人事業税については、事業税の事業区分に該当しない場合は課税されません。
住宅ローンを経費にするとのことですが、経費になるのは利息部分だけです。
また、事業分と家事分との按分はおおまかでも根拠が必要ですので、ご注意ください。
・節税の方法
・法人化すべきか
法人化することにより、節税が可能です。
但し、法人化するには費用が20-30万円必要になります。
・IT系の中小企業の役員が、別の会社を建てて問題ないか
役員になっておられる企業の事業内容によっては問題が生じるかもしれません。
取締役には会社に対する忠実義務があり、そのなかに競業避止義務というものがあります。
取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、会社の承認を受けなければならなりません(会社法356条)。
ただ、競業避止義務は会社組織であればダメで、個人事業であればいいというものではありません。
そのため、別の会社を設立するか否かの前に、競業避止義務の問題があるかもしれません。
・相談すべき相手
税金については税理士、会社設立については司法書士です。
当事務所でも相談を受け付けておりますので、お気軽ご相談ください。
以上、参考になれば幸いです。
開業費の申告の仕方
お世話になります。
月曜日に税務署に申告に行きます。
昨年9月から個人事業主として開業(個人事業の開業届けを税務署に提出)し、青色申告をするものです。
4ヶ月の売上(収入)は3万円。
2011年から2012年9月までの開業のための準備経費が80万かかりました(領収書あり)。
質問
?開業までにかかった準備経費は、申告決算書において、「開業費」という科目を立てて、そこに一式計上していますが、このやり方でよろしいでしょうか?
?今回の申告で、開業費を80万すべて申告するよりは、翌年、翌々年に少しずつ分けて申告するほうが、得するとある方から聞いたのですが、そうなのでしょうか?
そのような申告をしてもよいのでしょうか?例えば20万ずつ、4年に分けて開業費を申告するとか。。
よろしくお願いします。
月曜日に税務署に申告に行きます。
昨年9月から個人事業主として開業(個人事業の開業届けを税務署に提出)し、青色申告をするものです。
4ヶ月の売上(収入)は3万円。
2011年から2012年9月までの開業のための準備経費が80万かかりました(領収書あり)。
質問
?開業までにかかった準備経費は、申告決算書において、「開業費」という科目を立てて、そこに一式計上していますが、このやり方でよろしいでしょうか?
?今回の申告で、開業費を80万すべて申告するよりは、翌年、翌々年に少しずつ分けて申告するほうが、得するとある方から聞いたのですが、そうなのでしょうか?
そのような申告をしてもよいのでしょうか?例えば20万ずつ、4年に分けて開業費を申告するとか。。
よろしくお願いします。
Re:開業費の申告の仕方
大阪府岸和田市のたつだ会計事務所です。
開業費は、ご質問にあるように、繰延資産として「開業費」に一括計上してください。
但し、開業前であっても10万円以上の減価償却資産や均等償却をする必要のある繰延資産があれば、別途計上する必要があります。
開業までに掛かった家賃、水道光熱費、交通費、広告宣伝費などの諸費用であれば、まとめて計上してかまいません。
開業費を翌年や翌々年に分けて申告するというのは少し誤解があるように思います。
開業費は前述のとおり、繰延資産であり、経費項目ではありません。
開業費は資産として一括計上した後、経費計上(償却)するものです。
開業費の償却は、税法上は60か月均等償却又は任意償却のいずれかです。
任意償却は、開業費の範囲内の金額を償却費として認めるもので、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいとされています。
そのため、赤字の際には償却せず、黒字の時にのみ償却することも可能です。
また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
質問者様の場合、今回は繰延資産として資産計上するにとどめ、償却は次年度以降に利益の出具合を見ながらがよろしいかと思います。
以上、参考になりましたら、幸いです。
開業費は、ご質問にあるように、繰延資産として「開業費」に一括計上してください。
但し、開業前であっても10万円以上の減価償却資産や均等償却をする必要のある繰延資産があれば、別途計上する必要があります。
開業までに掛かった家賃、水道光熱費、交通費、広告宣伝費などの諸費用であれば、まとめて計上してかまいません。
開業費を翌年や翌々年に分けて申告するというのは少し誤解があるように思います。
開業費は前述のとおり、繰延資産であり、経費項目ではありません。
開業費は資産として一括計上した後、経費計上(償却)するものです。
開業費の償却は、税法上は60か月均等償却又は任意償却のいずれかです。
任意償却は、開業費の範囲内の金額を償却費として認めるもので、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいとされています。
そのため、赤字の際には償却せず、黒字の時にのみ償却することも可能です。
また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
質問者様の場合、今回は繰延資産として資産計上するにとどめ、償却は次年度以降に利益の出具合を見ながらがよろしいかと思います。
以上、参考になりましたら、幸いです。
確定申告の間違いと国民保険の停止
過去の確定申告の間違いに気づき、相談中ですが、当然国民保険料も関係してくると思います。
この場合、保険は一時停止になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
この場合、保険は一時停止になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re:確定申告の間違いと国民保険の停止
大阪府岸和田市のたつだ会計事務所です。
過去の確定申告に間違いがあり、税務署で修正申告(または更正の請求)をされようとしておられるんですね。
それであれば、以前から国民健康保険に加入され、きちんと保険料を納めているのであれば、過去の確定申告に間違いがあったからといって、国民健康保険証が使えなくなることはありません。
ただ、正しい所得で国民健康保険料の金額を算定されますので、金額によっては追加で国民健康保険料を支払うことになるか、もしくは還付を受けることができるかもしれません。
国民健康保険の追加支払いまたは還付があるか否かは、金額にもよります。ご心配であれば、市役所に相談されるとよいと思います。但し、実際の支払または還付は、修正申告または更正の請求について、税務署から市役所へ資料が回ってからになるはずです。
以上、参考になりましたら、幸いです。
過去の確定申告に間違いがあり、税務署で修正申告(または更正の請求)をされようとしておられるんですね。
それであれば、以前から国民健康保険に加入され、きちんと保険料を納めているのであれば、過去の確定申告に間違いがあったからといって、国民健康保険証が使えなくなることはありません。
ただ、正しい所得で国民健康保険料の金額を算定されますので、金額によっては追加で国民健康保険料を支払うことになるか、もしくは還付を受けることができるかもしれません。
国民健康保険の追加支払いまたは還付があるか否かは、金額にもよります。ご心配であれば、市役所に相談されるとよいと思います。但し、実際の支払または還付は、修正申告または更正の請求について、税務署から市役所へ資料が回ってからになるはずです。
以上、参考になりましたら、幸いです。
個人事業主です。
今年初めて青色申告をします。
青色申告はソフトを使用しています。
質問1
事業用100%で、車を購入(軽自動車)180万程度を購入しようと思います。現金で購入できればいいのですが、持ち合わせがなくローンもしくはリースで考えています。ローンの場合、月々のローン金額を経費計上できるのでしょうか?
また、頭金は軽自動車なら4年償却なので、4年間分割で経費計上したらいいのでしょうか?
質問2
自宅兼事務所で行っています。自宅は18時以降から朝までの使用なので、大半が事務所として考えています。
住宅ローン(築11年)の事務所部分の経費計上はどうしたらいいのでしょうか?
質問3
事務所兼自宅に太陽光発電の工事をしようかと思います。
事務所使用でデンキ代が上がってきたので・・その際もローンで行います。
事務所部分の経費計上はどのようにしたらよろしいですか?
多くなりしません。よろしくお願いします。
青色申告はソフトを使用しています。
質問1
事業用100%で、車を購入(軽自動車)180万程度を購入しようと思います。現金で購入できればいいのですが、持ち合わせがなくローンもしくはリースで考えています。ローンの場合、月々のローン金額を経費計上できるのでしょうか?
また、頭金は軽自動車なら4年償却なので、4年間分割で経費計上したらいいのでしょうか?
質問2
自宅兼事務所で行っています。自宅は18時以降から朝までの使用なので、大半が事務所として考えています。
住宅ローン(築11年)の事務所部分の経費計上はどうしたらいいのでしょうか?
質問3
事務所兼自宅に太陽光発電の工事をしようかと思います。
事務所使用でデンキ代が上がってきたので・・その際もローンで行います。
事務所部分の経費計上はどのようにしたらよろしいですか?
多くなりしません。よろしくお願いします。
Re:個人事業主です。
大阪府岸和田市のたつだ会計事務所です。
質問1について
ローンで購入する場合は、車を180万円の資産として計上する一方で、ローンを負債(借入金=180万円−頭金)として計上します。そのうえで、180万円の車につき、必要経費として減価償却費を計上します。
軽自動車の耐用年数は、記載されている通り4年ですので、4年で減価償却費を計算することになります。
リースの場合は、リース料で経費処理できる場合と、車を資産計上する必要がある場合がありますので、リース会社にご確認ください。
減価償却の詳細については、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm)に説明がありますので、ご参照ください。
質問2について
自宅兼事務所の場合、自宅の減価償却費や火災保険料などを使用割合に応じて按分することになります。
この場合の減価償却についても、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm)をご参照ください。
質問3について
こちらも資産(資本的支出)として計上する一方で、負債(借入金)を計上します。質問1と同様に減価償却費を使用割合に応じて按分することになります。
使用割合の按分については、ご自宅の減価償却費の場合、事業用と家事用の面積割合が妥当かと思います。
以上、参考になりましたら、幸いです。
質問1について
ローンで購入する場合は、車を180万円の資産として計上する一方で、ローンを負債(借入金=180万円−頭金)として計上します。そのうえで、180万円の車につき、必要経費として減価償却費を計上します。
軽自動車の耐用年数は、記載されている通り4年ですので、4年で減価償却費を計算することになります。
リースの場合は、リース料で経費処理できる場合と、車を資産計上する必要がある場合がありますので、リース会社にご確認ください。
減価償却の詳細については、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm)に説明がありますので、ご参照ください。
質問2について
自宅兼事務所の場合、自宅の減価償却費や火災保険料などを使用割合に応じて按分することになります。
この場合の減価償却についても、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm)をご参照ください。
質問3について
こちらも資産(資本的支出)として計上する一方で、負債(借入金)を計上します。質問1と同様に減価償却費を使用割合に応じて按分することになります。
使用割合の按分については、ご自宅の減価償却費の場合、事業用と家事用の面積割合が妥当かと思います。
以上、参考になりましたら、幸いです。
贈与税の非課税について
生命保険の契約者が成人してる子供、
被保険者が母親、
死亡受け取りが子供の契約の時、
毎年100万の保険料を母親が子供の口座に贈与として入金し 支払いした場合、
税務署に連続贈与とみなされるでしょうか?
保険会社は大丈夫といいますが、本当でしょうか?
これは6年間支払い、母親が死亡するまで据え置きする契約ですが、途中解約も可能です。
よろしくお願いします。
被保険者が母親、
死亡受け取りが子供の契約の時、
毎年100万の保険料を母親が子供の口座に贈与として入金し 支払いした場合、
税務署に連続贈与とみなされるでしょうか?
保険会社は大丈夫といいますが、本当でしょうか?
これは6年間支払い、母親が死亡するまで据え置きする契約ですが、途中解約も可能です。
よろしくお願いします。
Re:贈与税の非課税について
大阪府岸和田市のたつだ会計事務所です。
6年間支払う保険料を1年ごとに分けて、贈与したとみなされれば、連年贈与と言われると思います。
ただ単に、毎年現金100万円を贈与し、毎年贈与はしたけれども、そもそも、毎年贈与するかどうかは最初から決めてたわけではない場合であれば、非課税枠110万円の範囲ですから、贈与税はかかりません。
また、現金100万円を贈与する際は(振込であっても)、契約書を作成し、親子の印鑑を押印しておきましょう。慎重にするなら、確定日付を取ったほうがいいです。
契約者がお母様なら、このような問題は起きないのでしょうが、相続対策でしょうか。
相続対策であれば、税理士に相談することをお勧めします。
以上、参考になれば幸いです。
6年間支払う保険料を1年ごとに分けて、贈与したとみなされれば、連年贈与と言われると思います。
ただ単に、毎年現金100万円を贈与し、毎年贈与はしたけれども、そもそも、毎年贈与するかどうかは最初から決めてたわけではない場合であれば、非課税枠110万円の範囲ですから、贈与税はかかりません。
また、現金100万円を贈与する際は(振込であっても)、契約書を作成し、親子の印鑑を押印しておきましょう。慎重にするなら、確定日付を取ったほうがいいです。
契約者がお母様なら、このような問題は起きないのでしょうが、相続対策でしょうか。
相続対策であれば、税理士に相談することをお勧めします。
以上、参考になれば幸いです。
同じ地域で検索する
その他の税理士
よく検索されるキーワード
- 定款|
- 小規模企業共済|
- 農業|
- 相続|
- 堀口会計|
- 土地建物名義変更|
- 東京 税理士|
- 顧問料|
- 税理士紹介|
- 株式譲渡契約書|
- 税理士 武蔵野市|
- 医療費控除|
- 特別縁故者|
- 税理士会|
- 公証人役場|
- 相続税|
- 配偶者控除|
- 税金対策|
- 扶養控除|
- 給与計算|
- 必要経費|
- 相続税 相談|
- 飲食店 税理士|
- 港区 会計事務所|
- 労災|
- 限定承認|
- 給与 税金|
- 白色申告|
- 土地の贈与|
- 使途不明金|
- 帳簿|
- 建設業手続代行|
- 会社法|
大阪税理士紹介センターの税理士検索をお使いのうえで、ご不明な点がございましたら、よくあるご質問をご覧ください。
よくあるご質問で解決できない問題や、その他ご意見などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。